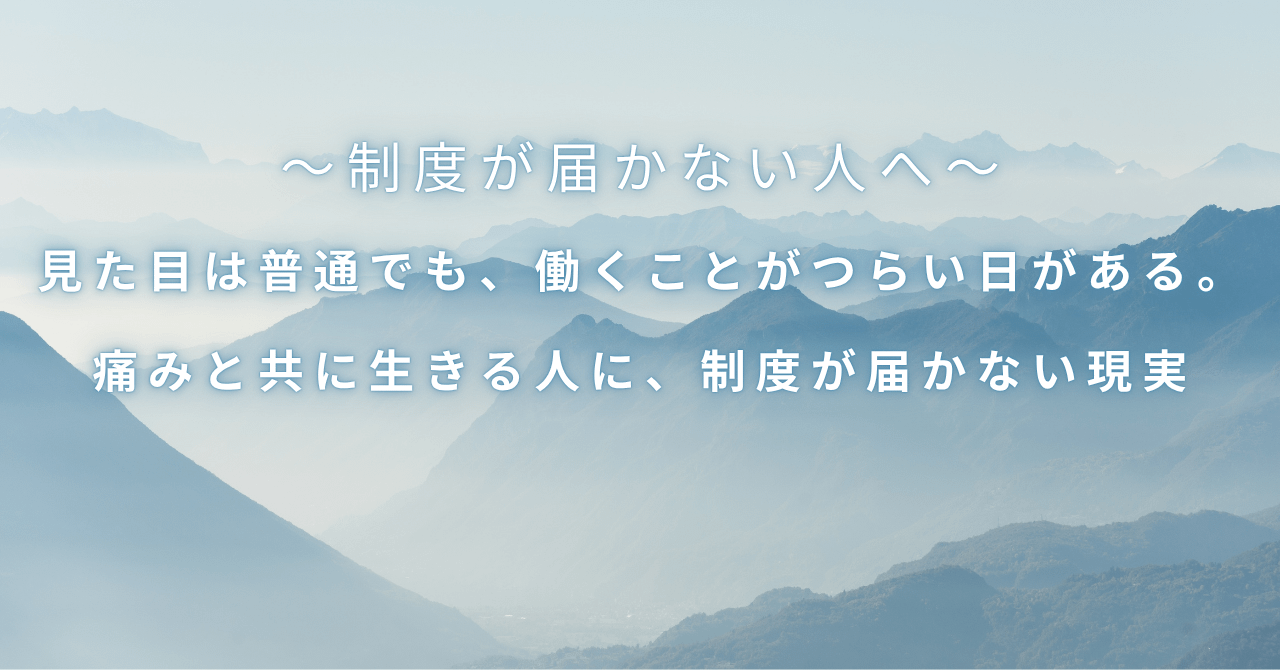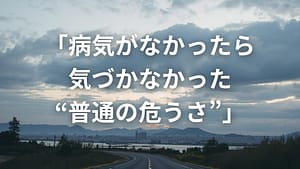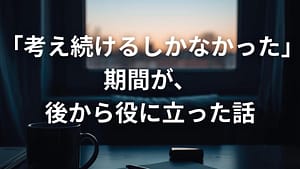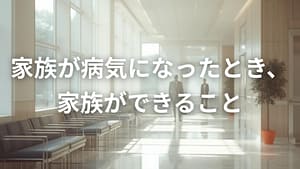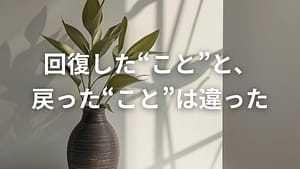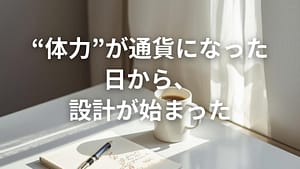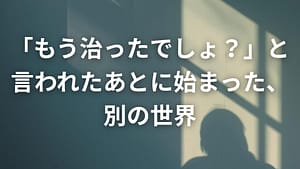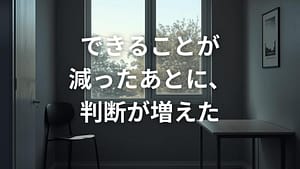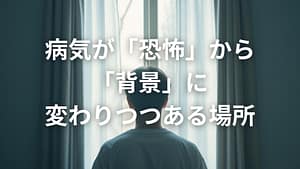制度があるのに、救われない人がいる。
その現実を、ようやく自分の身をもって知った。
退院してからの数か月。
外から見れば、私はもう「元気になった人」に見えるかもしれません。
でも実際は、朝の動き出しに時間がかかり、胸、背中、足の痛みのほか、
座っているだけでお尻にじんわりと痛みが広がる日もあります。
在宅で仕事をし、できる範囲で体と折り合いをつけながら少し働いています。
それでも時折、「もしこの先、働けなくなったら……」と不安がよぎります。
そんなとき、頭をよぎったのが障害者手帳という制度でした。
けれど調べてみると、
“痛み”や“しびれ”だけでは対象にならないケースも多い。
今日は、「支援の仕組みがあっても、届かない人がいる」という現実を、
私自身の視点で静かに書いてみます。
痛みは“見えない障害”になることがある
手術後、痛みやしびれは日常の一部になりました。
「治った」と言われても、痛みが消えるわけではありません。
身体が回復しても、神経の痛みは別の次元に残る。
けれど、外から見れば私は“普通の人”に見えます。
歩けるし、話せる。
だから「大丈夫そう」と思われる。
本当は、痛みを我慢して立っているだけの日もあるのに。
「元気そう」と言われると、つい笑顔で返してしまう。
“見えない障害”とは、そうした理解されにくい痛みや、伝えにくい苦しみのことだと思います。
体の内側にある不具合ほど、他人には気づかれにくい。
それが一番のつらさです。
線を引かれる現実 ― 身体障害者手帳の壁
障害者手帳と聞くと、
「困っている人なら誰でも支援が受けられる制度」と思う人も多いかもしれません。
けれど実際には、明確な認定基準があります。
身体障害者手帳は、
運動機能や感覚器官など、目に見える機能障害を対象としています。
そのため、私のように日常生活は送れても慢性的な痛みがあるケースでは、
認定を受けることが難しいのが現実です。
夜、痛みで眠れない。
翌朝、体が思うように動かず、仕事を休む。
そんな日が続いても、診断書の数字の上では「支障なし」とされてしまう。
制度は必要です。
でもその線の外側に立たされる人がいる。
それが、この“グレーゾーン”と呼ばれる世界です。
身体の痛みが理解されない現実の裏には、
「痛みが続くことで心まで疲弊する」という別の問題もあります。
「精神障害者保健福祉手帳」というもう一つの可能性
慢性的な痛みや不眠、不安感が続くと、
精神的な負担が蓄積し、うつ状態に近づくこともあります。
痛み止めとして処方される抗うつ薬や抗てんかん薬。
一見「心の薬」に見えても、神経の興奮を鎮めるために使われることもあります。
私も後遺症による痛みで、抗うつ薬、抗てんかん薬を飲んでいます。
こうしたケースでは、
精神障害者保健福祉手帳の対象になる可能性もあるそうです。
ただし、これは医師の診断と自治体の判断によって決まるもの。
「取る」「取らない」を自分で判断することはできません。
私は、今すぐ申請を考えているわけではありません。
けれどもし将来、痛みや不安で仕事が難しくなったとき、
その選択肢があることを知っている――
それだけで、少し心が軽くなる気がします。
会社員として働くことに感じた不安と、フリーランスという選択
術後、私は会社員として働くことに大きな不安を感じていました。
なぜなら、会社で働けば“健常者”として扱われますが、
実際は 痛み・リハビリ・通院 のため、どうしても他の人より休む回数が増えてしまう。
その状況が怖かったのです。
だから私は、
「このまま会社員を続けるのは難しい」
と判断し、自分のペースで働けるフリーランスという道を選びました。
しかしフリーランスは、働けなければ収入がゼロになります。
今でも痛みで働けない日がありますし、働けても長時間は体がもちません。
痛みが出る前に仕事を切り上げることもしばしばです。
だからこそ、
短い時間でも成果を出せるように、仕組化や資産化を進めている
というのが、今の私の働き方です。
もしあの頃、精神障害者保健福祉手帳が取れる可能性を知っていたら──
会社員のまま働き続けていたかもしれません。
痛みが出れば働けない。
働けない日は収入がない。
不安にならないと言えば、それは嘘になります。
フリーランスの現実の厳しさを知っているからこそ、
同じように苦しむ人が少しでも減ればと思い、
こうした制度の存在を記事にしました。
努力できる人ほど、限界まで我慢してしまう
私は、なるべく人に頼らず、自分でできることを増やしてきました。
仕事のペースを調整し、体の声を聞きながら日々を組み立てる。
それが、私なりの「自助努力」です。
けれど、誰もがそうできるわけではありません。
痛みや倦怠感が強く、働くこと自体が困難な人もいます。
周りの理解が得られず、孤立してしまう人もいます。
「支援を受けること=甘え」という空気が、
まだこの社会には根強く残っています。
でも、支援を受けることは逃げではなく、再び歩き出すための手段です。
それを恥じる必要はありません。
社会が用意してくれた制度は、“弱さ”を証明するものではなく、
「生き延びるための橋」なんです。
まずは“調べてみる”という選択を
もし痛みや不安で生活に支障を感じているなら、
まずは自分の状態を整理してみてください。
- 診療明細や薬の内容をまとめておく
- 症状の変化や通院の頻度をメモする
- 医師に「日常で困っていること」を具体的に伝える
これだけでも、自分を客観的に見つめる手がかりになります。
その上で、
「○○市 障害福祉 相談窓口」
などで検索すると、公式の相談先が見つかります。
制度を“使う”かどうかよりも、
まずは「知ること」から始める。
それが、最初の小さな一歩です。
制度が届く社会へ ― 私が願うこと
私は、制度そのものを否定したいわけではありません。
むしろ、こうした仕組みがあることが希望です。
ただ、線の内側と外側のあいだにある「見えない壁」が、
多くの人を静かに苦しめていると感じます。
「見た目は普通」
「自立しているように見える」
でも、その裏に、痛みや不安を抱えて暮らしている人がたくさんいる。
その人たちにも、制度の光が届くように。
私は、その橋の上で言葉を書き続けたいと思っています。
さいごに
制度を知ることは、自分を守ることです。
たとえそれを使わなかったとしても、
「もしもの時、こういう支えがある」
と知っているだけで、少しだけ未来の不安がやわらぎます。
私は、今日も痛みと向き合いながら働いています。
正直に言えば、楽ではありません。
それでも、こうして書くことで、
“自分を支える言葉”をひとつずつ見つけている気がします。
どうか、“頑張るしかない”という言葉の下で、
苦しむ人がこれ以上増えませんように。
支援が、必要な人に、きちんと届く社会でありますように。
※本記事は筆者の経験および公開情報をもとに作成しています。
障害者手帳の適用可否は、医師の診断および自治体の判断によって異なります。
具体的な手続きや相談は、必ずかかりつけ医・自治体窓口・専門機関にお問い合わせください。