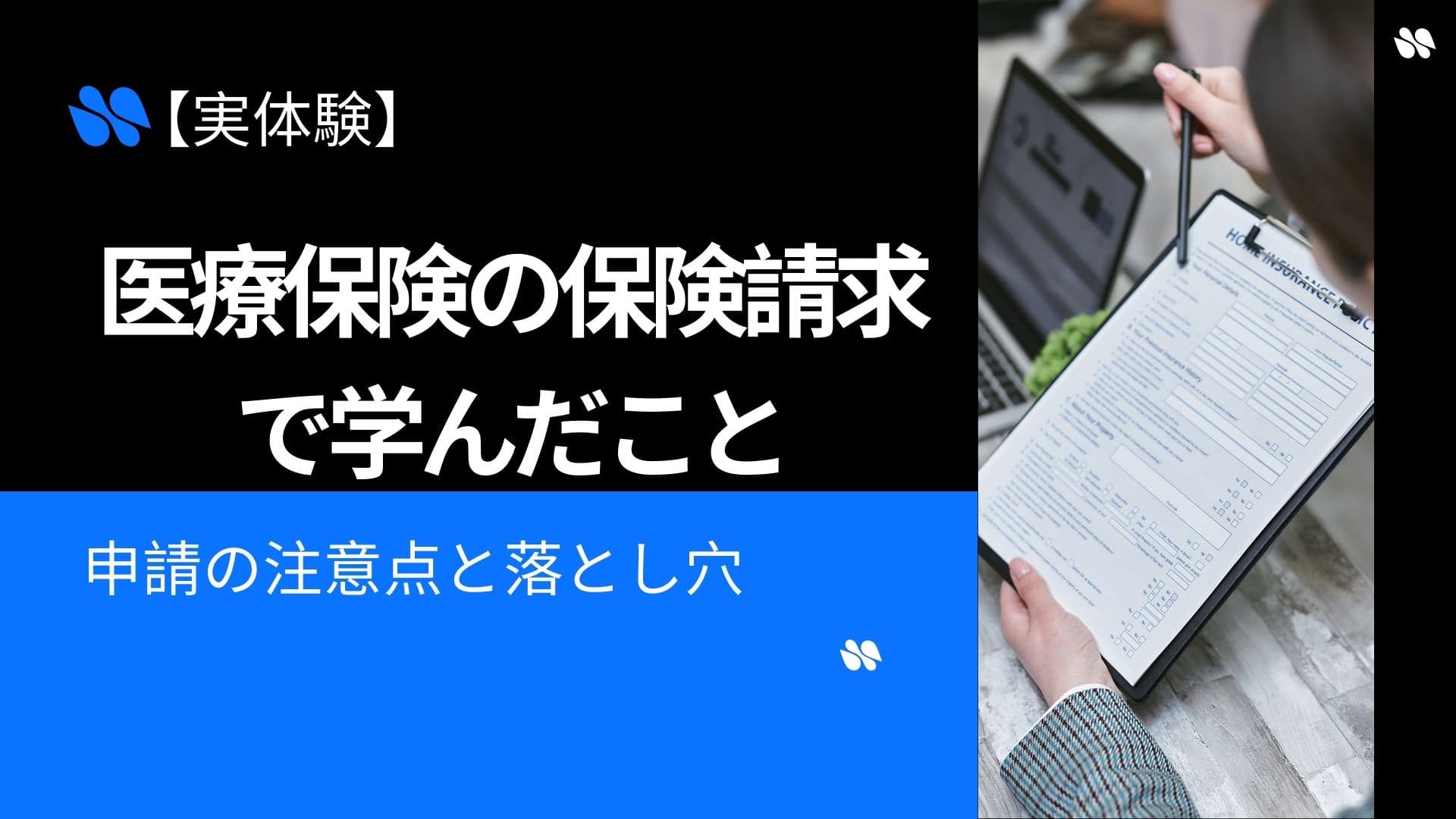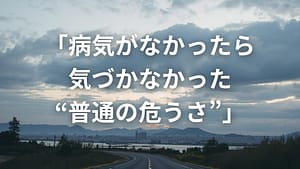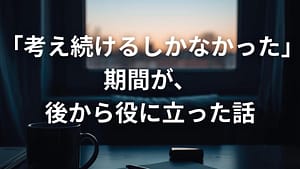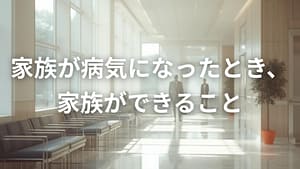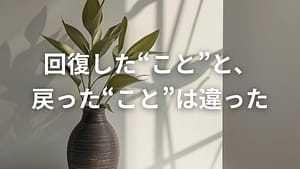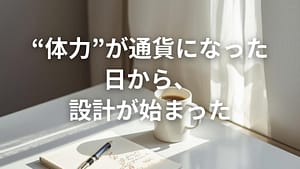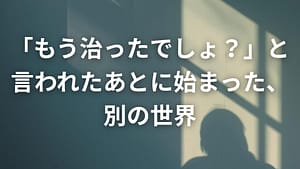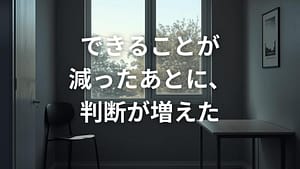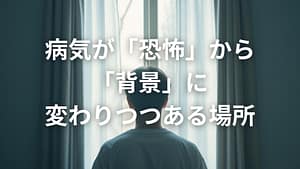【体験談】医療保険の保険金申請でわかったこと|申請の注意点とがん保険の落とし穴
入院や手術を経験すると、医療保険のありがたみを改めて感じます。この記事では、私自身の保険金申請の体験談と、友人(がん経験後に保険営業をしている方)から聞いた「がん保険の落とし穴」を、初心者向けにやさしくまとめました。保険の見直しを考えている方の参考になればうれしいです。
体験談:実際に受け取った保険金の内訳
私は、2024年に脊髄腫瘍の手術で3週間の入院をしました。退院直後は体調も安定せず、保険の手続きに手が回りませんでした。数か月後、ようやく申請して振り込まれたのは次のとおりです。
- 手術一時金:20万円
- 入院給付金:9万円(日額5,000円、18日分)
合計:29万円
実際に病院へ支払った医療費は、高額療養費の上限を超えた金額と合わせて約18万円。差し引きで約10万円のプラスとなりました。差額ベット代と入院期間が月を跨いで2か月分になりましたので支払が多くなりました。
主治医からは「もう少し入院して様子を見ますか?」と声をかけていただいたのですが、私は「早く自宅に帰りたかったので、いいえもう帰って家で療養します。」と早めに退院。
入院経験のある方なら分かるはずです。病院生活は退屈で、一日でも早く家に帰りたい気持ちが勝つんですよね。
【補足】
私が入っていた保険は、月額数千円のいわゆる掛捨ての医療保険です。
・手術時:一時金
・入院時:5,000円/1日(がんの時も同様)
・死亡時:1000万円(病気・災害時)
保険金申請でつまずきやすい2つのポイント
1. 「保険会社指定の診断書」は必須
請求には保険会社指定フォーマットの診断書が必要です。発行には数千円〜1万円超かかることもあります。
はっきりした値段は覚えていませんが、私は約8000円の費用がかかりました。私は保険会社から専用の用紙を貰って病院に記入の依頼をしたのですが、そこは病院も慣れています。
ネットでダウンロードして、必須事項をPCで入力して、印鑑をした書類を用意してくれました。
更に、私は診断書を貰ってから、保険会社に請求書を出すのが遅くなってしまい、診断書のフォーマットが変わっていたのです。幸いなことに、旧式の診断書でも審査が通ったので良かったのですが、万一審査に影響あれば、診断書の取り直しもあるみたいです。
診断書を貰うとすぐに保険会社に請求される方がよいと思います。
- 事前に診断書のフォーマットをダウンロード若しくは用紙を入手しておく
- 記入担当科(主治医 or 医事課)を確認
- 発行日数と費用を確認(受付窓口)
この3点を押さえておくとスムーズです。
2. 請求期限(時効)に注意
多くの民間医療保険では請求の時効は3年が一般的です。私は申請まで約8か月かかり、その間に診断書の書式が変更されておりヒヤッとしました。事情を説明して通りましたが、早めの申請を強くおすすめします。請求より体を早く治したいとリハビリに専念していたので、申請が遅くなってしまいました。
ワンポイント:
領収書・明細・診療計画書・退院サマリーなど、関連書類は封筒ひとつにまとめて保管。後からの書類確認や確定申告(医療費控除)の際にも役立ちます。※確定申告時の医療費控除は、病院に支払った保険料から医療保険で支給を受けた収入を差し引いて支出が越える場合、確定申告すれば還付を受けれます。
古い「がん保険」に潜む落とし穴5つ
医療は進歩し、治療は短期入院・通院中心にシフトしています。一方で古い契約のがん保険は当時の基準のまま、ということも。代表例は次のとおり。
- 先進医療が対象外
陽子線・重粒子線などは特約がないと対象外。自己負担が数百万円に及ぶ可能性も。 - 通院治療が非対象
古い契約は「入院が給付条件」。通院で抗がん剤治療を受けても支払われないケース。 - 診断一時金なし
がんと診断された時にすぐ使えるまとまった資金が出ない。初動の費用準備に影響。 - 上皮内新生物(早期がん)が対象外/減額
乳がん・子宮頸がんなどの初期段階が対象外、もしくは減額になる契約も。 - 入院日数要件が古い
「5日以上入院」などの条件が残っており、日帰り・1泊手術だと対象外に。
いまの医療に合っているか?見直しチェックリスト
- 先進医療特約:あり/なし
- 診断一時金:あり/なし(がん種・回数の条件も確認)
- 通院治療:対象/対象外
- 上皮内新生物:対象/減額/対象外
- 入院日数要件:なし(初日から)/あり
- 更新・保険料:年齢上昇での負担増は許容範囲?
- 他の保険・公的制度との重複や過不足はないか?
10年以上前の契約は、一度コールセンターで保障内容を棚卸しするのがおすすめです。書面やマイページで最新の約款・重要事項説明を確認しましょう。
※加入していても、給付要件と合致せず想定どおり受け取れない場合があります。定期的に約款と治療状況のズレを点検する見直しをおすすめします。
私の結論:保険は「必要な補償に絞った掛け捨て」+資産形成は投資で
独自の見解ですが、私は公的制度を踏まえたうえで、掛け捨ての医療保険で必要な補償を確保し、資産形成はNISAやETFなどの株式投資で分けて行うほうがシンプルで効率的だと考えています。
積立型の保険は、保険料の中に「保障にかかる費用」「運用部分」「付加費用」など複数の要素が含まれ、内訳は商品ごとに異なります。私は公的制度や家計の状況を踏まえ、保障と資産形成は分けて設計する方が目的管理しやすいと感じています。
もちろん、医療保険やがん保険はライフステージや家族構成によって必要性が変わるため、私の考えがすべての方に当てはまるわけではありません。
大切なのは、「自分に必要なリスクにどう備えるか」を理解して選ぶことだと思います。
※本記述は一般的な考え方と私見であり、特定商品の優劣を断定する意図はありません。加入可否は各社の約款・費用体系・税制優遇等をご確認ください。
まとめ
- 実体験として、医療保険は実際に役立った
- 申請では診断書の形式と請求期限(3年目安)に注意
- 古いがん保険は通院非対象・先進医療非対応・上皮内新生物除外などの落とし穴に要注意
- 見直しチェックリストで、いまの医療に合っているかを確認
- 保険は掛け捨ての医療保険+資産形成は投資で分ける方針が管理しやすい(私見)
よくある質問(FAQ)
Q1. 保険金の請求は退院後すぐでないとダメ?
A. 多くの医療保険で3年の時効が一般的ですが、書式変更などのリスクもあるため早めの申請が安心です。
Q2. 診断書は病院の書式でいい?
A. 原則、保険会社指定のフォーマットが必要です。発行費用・日数も事前確認を。
Q3. 先進医療特約は入ったほうがいい?
A. がん種・年齢・家計方針によります。技術料が高額になり得るため、加入の有無で自己負担の差が大きくなる点は理解しておきましょう。
Q5. 古い保険をそのまま続けると注意点はありますか?
A. 一概に「危険」とは言えませんが、医療の進歩と契約条件のズレがあると給付が受けられない可能性があります。10年以上前に加入した契約は、最低でも一度「現在の治療法に対応しているか」を確認しておくことをおすすめします。
Q6. 保険金をもらったら税金はかかる?
A. 医療保険・がん保険の給付金は、基本的に「非課税」です。ただし、法人契約や一部の給付(所得補償など)は課税対象になることもあるため、個人契約なら原則非課税と覚えておけば安心です。
Q7. 保険と貯金、どっちを優先すべき?
A. 基本は「生活防衛資金(貯金)」を優先し、その上でリスクに備えるために医療保険を活用するのがバランスの良い考え方です。保険は「いざという時の補填」、貯金は「すぐ使える自己防衛資金」と役割が異なります。