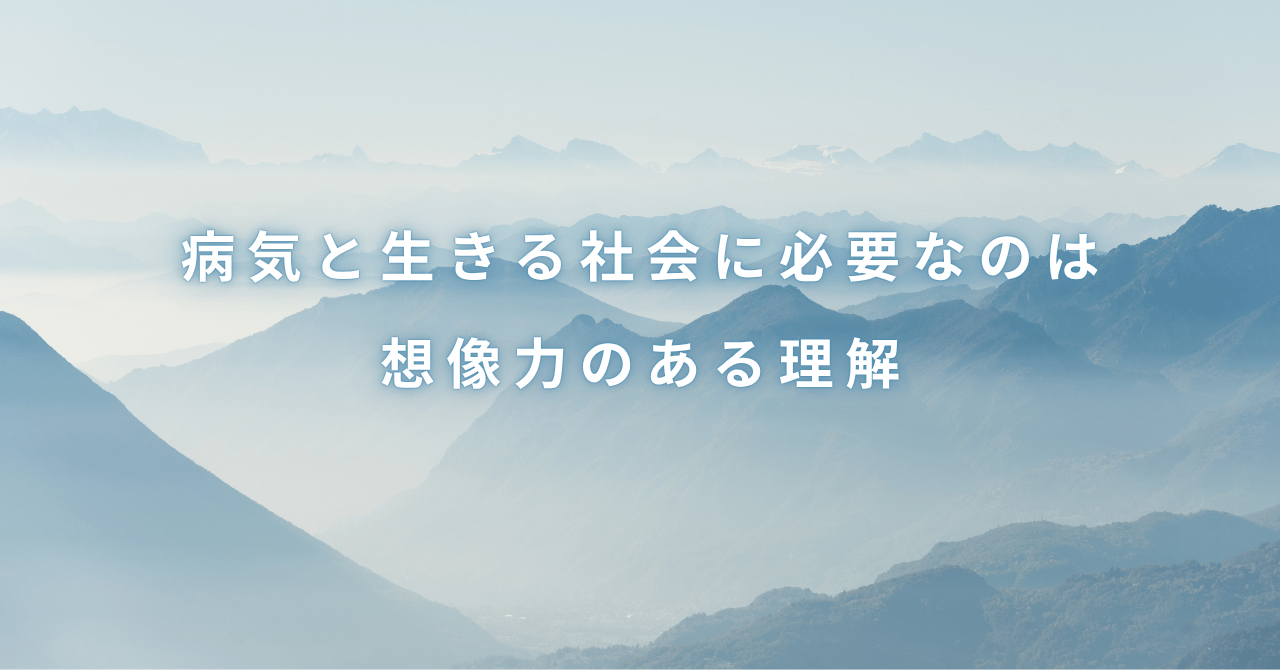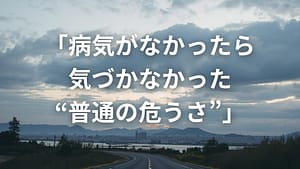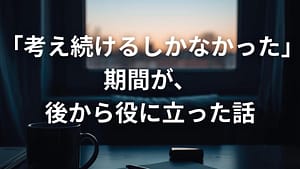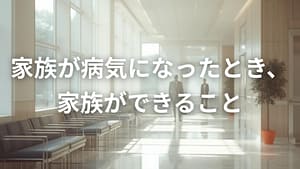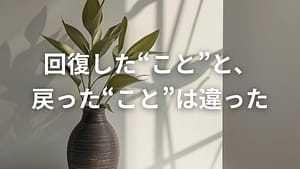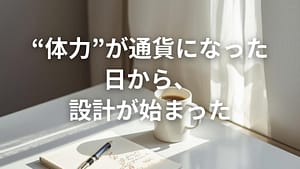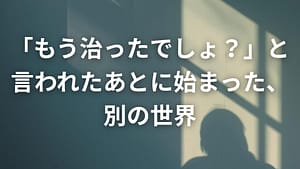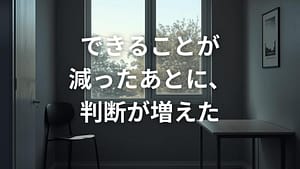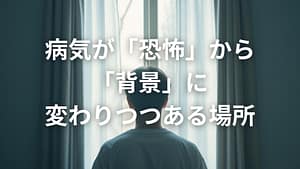私は脊髄腫瘍を経験し、手術とリハビリを経て、今も後遺症と共に生きています。
歩けるようにはなりましたが、日によっては体が痛み、思うように動かない日もあります。
外から見れば「元気そう」に見えるかもしれません。
けれど、病気と生きる人の多くは“見えない不自由”を抱えています。
今日は、私自身の経験をもとに、
「病気と生きる社会に本当に必要な“理解”とは何か」を考えてみたいと思います。
「理解されない苦しさ」は、痛みよりも深い
退院した直後、私は“社会復帰”という言葉に強いプレッシャーを感じていました。
周囲からは「もう退院できたんだから良かったね」「元気そうで安心した」と言われました。
もちろん、それは善意からの言葉です。
けれど心の中では、こう思っていました。
「本当はまだ痛く、痺れや麻痺もあるんです。歩くのも怖いんです。」
病気そのものの痛みよりも、「理解されないことの孤独」のほうがずっとつらかった。
誰かの励ましや「退院できて良かったね」という言葉も、時に自分を追い詰めることがあります。
この「見た目と実際のギャップ」こそ、社会の理解がまだ追いついていない部分だと感じています。
退院=病気治ったと認識される事が多かったからです。
私は、脊髄の圧迫損傷からの後遺症ですが、精神疾患など目に見えにくい病気も同じだと個人的には思っています。
「共感」ではなく「想像」から始まる理解
「共感します」という言葉は優しく聞こえますが、実際にその人の痛みを完全に理解することはできません。
共感は“経験したことがある範囲”にとどまるからです。
本当に必要なのは、「自分には分からないけど、想像してみよう」という姿勢。
たとえば──
- 電車で座っている若い人を見ても、「怠けてる」ではなく「痛みがあるのかも」と思う。
- 休職中の人に「早く戻れるといいね」ではなく、「焦らず休めてる?」と声をかける。
- 体調の波がある人に「昨日はできたのに」ではなく、「今日は無理しなくていいよ」と言う。
小さな“想像の積み重ね”が、社会をやさしくしていきます。
「助けて」と言えない社会を変えるには
多くの人が「迷惑をかけたくない」「弱音を吐きたくない」と思っています。
私自身もそうでした。
たとえ体がつらくても、「いや大丈夫です」「まだ頑張れる」と自分を奮い立たせる。
でも、無理を重ねれば、心も体も限界を迎えます。
なぜ「助けて」と言いづらいのか。
それは、“助けを求める=弱い”我慢が足らないとする空気が、社会にまだ残っているからです。
本来、「助けて」と言えることは勇気であり、信頼の証でもあります。
「助けを出せる社会」こそ、やさしい社会の第一歩だと思います。
職場に必要なのは「体調に合わせた仕組み」
病気と働く人が最もつまずくのは、職場の理解です。
フルタイム勤務が難しい、急な通院がある、体調が日によって違う──
そんな事情を「特別扱い」と見なす空気感がまだあります。
けれど実際は、柔軟な働き方を認めることが“長く働ける人”を増やすことにつながります。
私がフリーランスという働き方を選んだのも、「体調の波を前提に働くため」でした。
週に数日でも、自分のペースで社会とつながること。
それが、再び自分を取り戻すための第一歩でした。
企業も「健康な人だけが働ける場所」でなく、「誰もが体調に合わせて働ける仕組み」であればよいのにと、病気になって深く考えさせられました。
週40時間を前提とした雇用形態。
この働き方の見直しが、人材不足と言われているこれからの社会に求められる新たな雇用ではないかと思います。
少なくとも、私は週40時間を前提とした社会にはあてはめることが出来なかったので、自分で仕事をすることを選択しました。
支える側にも“ケア”が必要
病気と生きるのは本人だけではありません。
家族やパートナー、同僚など“支える側”もまた、心の負担を抱えています。
「どう声をかけたらいいのか分からない」
「励ましたつもりが、逆に傷つけてしまったかもしれない」
そう感じる人も多いでしょう。
支える人が孤立しないためには、「完璧に支えよう」としないことが大切です。
できる範囲で寄り添い、ときには一緒に泣いたり、ただ隣にいるだけでいい。
支える側のケアもまた、“理解ある社会”の一部です。
SNS発信が「理解」を広げる力になる
今の時代、病気と生きる人が自分の体験を発信できるようになりました。
私もnoteやWordPressで、自分の病気や働き方について発信しています。
最初は「こんなことを書いて意味があるのか」と迷いましたが、同じように病気と向き合う方からメッセージをいただくたびに、「自分だけじゃない」と感じられるようになりました。
SNSには批判もありますが、
“共感や想像を広げる力”という点で、これほど有効なツールはありません。
誰かの発信が、別の誰かの生きる力になる。
それが今の時代の“支え合いの形”なのかもしれません。
理解の第一歩は、「知ろう」とすること
病気と生きる人が求めているのは、特別な扱いではありません。
「知ってもらうこと」「理解しようとしてもらうこと」。
「なぜできないの?」ではなく、「どうすればできる?」と考える。
その一歩が、誰もが生きやすい社会をつくります。
そして、私たち一人ひとりもまた、いつ病気や不調を抱える立場になるか分かりません。
だからこそ、「誰かのため」ではなく「いつかの自分のため」に、理解を育てていく必要があります。
まとめ|“理解”とは寄り添う想像力
病気と生きる人が安心して暮らせる社会に必要なのは、
「かわいそう」でも「がんばって」でもなく、想像力のある理解です。
- 見えない痛みを想像すること
- 弱音を受け止めること
- 自分もいつか支えられる側になるかもしれないと知ること
それが、“やさしい社会”の本当の意味。
私もまだ完全に受け入れられたわけではありません。
けれど、こうして言葉にすることで、少しずつ前に進めています。
もしこの記事が、誰かの理解や行動のきっかけになれば、
それだけで書いた意味があると思っています。