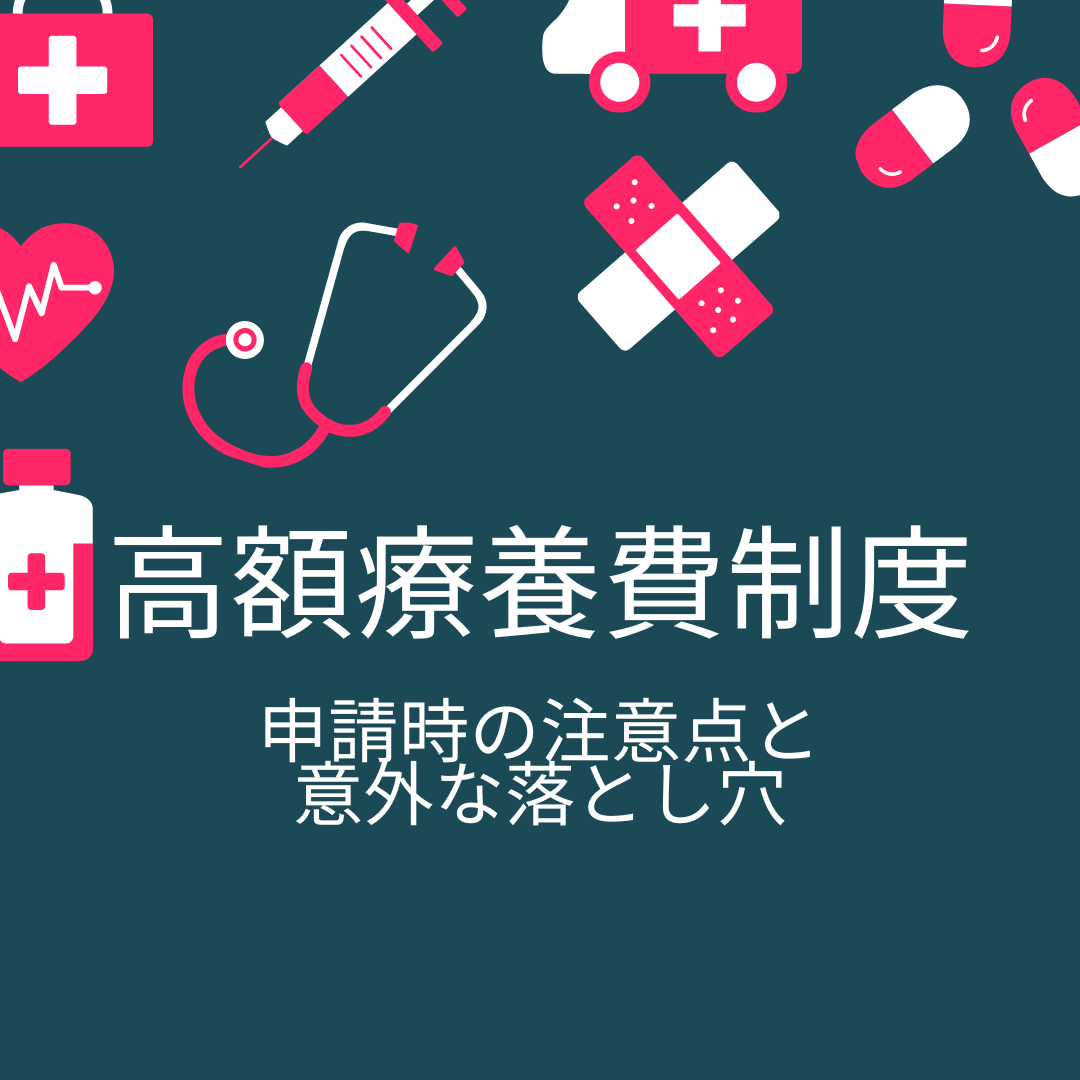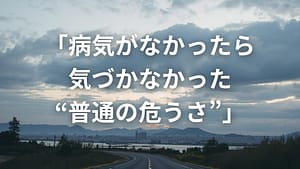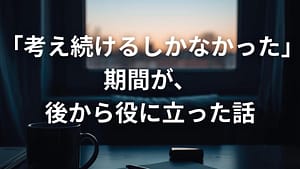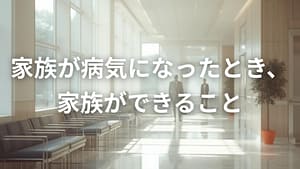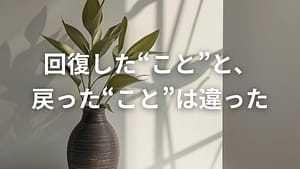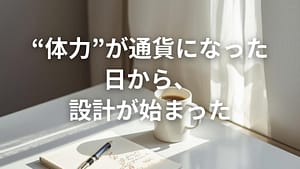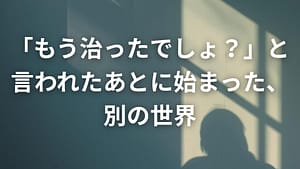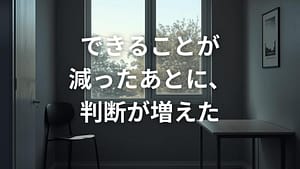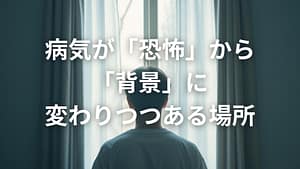私は脊髄腫瘍の手術と長期入院を経験しました。
その際に活用した制度のひとつが「高額療養費制度」です。
この制度を事前に知っていたおかげで、実際の窓口支払いは“還付待ち”ではなく、最初から高額療養費を差し引いた金額だけで済みました。いわゆる「限度額適用認定証」をあらかじめ取得していたためです。
今日はその実体験をもとに、これから入院や手術を控えている方に向けて、高額療養費制度を上手に使うための注意点と意外な落とし穴をお伝えします。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1か月(1日〜月末)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。所得に応じて上限額が定められており、対象となるのは「健康保険の自己負担分」です。
この制度には2つの使い方があります。
- ① 事後申請による還付型(いったん支払ってから後で戻る)
- ② 「限度額適用認定証」を提出して事前適用型(最初から還付額が差し引かれる)
私は②の方法で申請していたため、退院時にはすでに高額療養費が差し引かれており、実際の支払いは上限額まででした。
この仕組みを知らないまま入院すると、数十万円を立て替えなければならないこともあるため、事前申請の有無が大きな差になります。
注意点①:事前申請をしておけば「立て替え不要」にできる
入院が決まったら、すぐに加入している健康保険(または国保)へ「限度額適用認定証」を申請しましょう。郵送でも対応可能です。
この証明書を提出しておけば、退院時に上限額を超える部分は請求されません。
一方、申請をしていなかった場合は、いったん全額支払い、数か月後に還付を受ける流れになります。
- ポイント:退院時に「認定証を提出したかどうか」で支払い金額が変わります。
- 事前準備:入院前に健康保険組合や国保のサイトから申請用紙をダウンロード。
※病院ごとに異なってくると思いますが、私が通っていた病院では病院側でこの手続きをしてくれました。自分自身で取らないとダメなのか、一度窓口で確認されるとスムーズに手続きができます。
注意点②:月単位で計算されるため「入院時期」で金額が変わる
高額療養費は1日から月末までの“月単位”で計算されます。
そのため、入院期間が月をまたぐと、それぞれの月で上限額が適用され、結果的に支払いが増えることがあります。
例えば、2週間の入院でも月末から翌月にかけて入院すると、2か月分の計算になります。
逆に、月初から月末に収まるようにすれば1か月分の上限で済みます。
私自身、手術を出来るだけ早くしたかったので、選択権がなく月の下旬に入院して手術しました。その結果2か月に渡る入院生活となり、費用が2か月分と大きくなりました。もし緊急性がなく入院日・手術日を医師と相談して決めれる長期入院の場合は、月初に入院するスケジュールでその月中に退院できるようにすることをおすすめします。これにより、自己負担額を最大限に抑えることができます。
- ポイント:入院や手術日を調整できる場合は、なるべく月初から。
- 理由:月をまたぐと上限がリセットされる。
注意点③:差額ベッド代は自費。ただし請求されないケースもある
差額ベッド代(個室料金)は基本的に自己負担です。
ただし、大部屋が満室で個室しか空いていない場合など、病院の都合で個室を案内された際は、差額が請求されない場合があります。
私の場合は、個室を希望していたのですが大部屋しか空いておらず、実際には経験していませんが入院前に色々な情報を調べていて、差額ベット代を請求されないケースもあることを知りました。
病院によって対応が異なるため、入院前に必ず確認することをおすすめします。
- ポイント:「病院都合」の場合は免除されることもある。
- 確認先:入院受付または医療相談窓口。
注意点④:差額ベッド代の「日数計算」にも注意
これは病院によって取扱いが異なるそうですが、病院の宿泊代は1泊2日=2日分で計算されることがあります。
つまり7泊8日なら8日分の請求という形です。ホテルのように「1泊=1日分」ではないので費用的に気になる方は事前に確認下さい。
すべての病院が同じとは限りませんが、思ったより高くなるケースもあるので、入院前に日数の数え方を確認しておくと安心です。
注意点⑤:交通費・駐車場代・食事代は対象外
高額療養費の対象は「医療機関に支払った医療費」のみです。
通院交通費、駐車場代、食事代、日用品などは含まれまず、自己負担となります。
※特に気になったのは、食事代です。入院時食欲があまりなく、ほとんどご飯を残していました。それでもきっちりと3食分請求に含まれます。病院食はカロリー計算もされていて健康的なのですが、味気なく量も控えめで、1食約500円かかっていました。外食するよりは安いのですが、私は食事制限がある病気じゃなかったので、コンビニでおにぎりなど買って食べていました。なので、無駄な費用だったなと思いました。
また、上記の費用は確定申告で医療費控除の対象になります。領収書や交通費メモを残しておくと、後で控除に活用できます。
- ポイント:高額療養費で対象外の支出は医療費控除でカバー。
- 準備:年間のレシート・交通費記録をまとめておく。
注意点⑥:保険組合や自治体によって上限額が異なる
同じ制度でも、加入している健康保険組合・協会けんぽ・国保などによって、上限額の計算や申請方法が微妙に異なります。
ネットの一般表をそのまま鵜呑みにせず、自分の保険者の公式サイトで上限額を確認するのが確実です。
- 検索例:「高額療養費 〇〇保険組合」
- 不明点:電話で聞くのが最も早く正確。
注意点⑦:同月・同一世帯で合算できる
同じ世帯で複数人が医療費を支払った場合は、世帯合算が可能です。
また、同一人物が複数の医療機関を利用した場合も、同月内であれば合算されます。
ただし、月をまたぐと合算できなくなるため、領収書は月ごと・人ごとに整理しておくのがおすすめです。
実際に使って感じたこと
高額療養費制度は、本当に助けになる制度です。
私自身、事前に認定証を取得していたことで、退院時の立替払いがなく支払いを大幅に減らすことができました。
同時に、「月単位の計算」「差額ベッド代の扱い」「病院による違い」など、実際に使ってみないと気づかない点も多くあります。
これらを事前に理解しておくだけでも、心の余裕が全く違います。
まとめ:制度を「理解して使う」ことが大切
高額療養費制度は知っているだけでは足りません。
申請のタイミングや入院時期の工夫で、支払い金額が大きく変わることがあります。
限度額認定証の事前申請、入院日程の調整、差額ベッド代の確認など、ほんの少しの準備で家計の負担はぐっと減らせます。
病気は誰にでも起こり得ます。
元気なうちに「自分の制度」を理解し、いざという時に迷わず使えるようにしておく。
それが、自分と家族を守る最善の備えだと感じています。